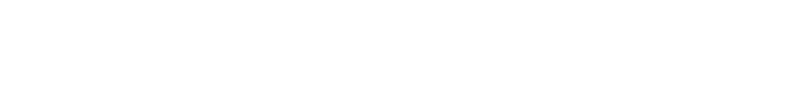投稿日 2025/08/18
いきなり結論から言いますが、良くないです。空冷のポルシェが現代の水冷のポルシェに性能で敵わないのと同じで、古い乗り物に過大な幻想を抱いてはいけません。自転車の場合タチが悪いのが、空冷のポルシェのように乗り心地の悪さが、感性に訴えかけるポジティブな何かに変換されないことです。
とは言え、古い自転車には現代の自転車にはない独特の雰囲気があります。僕が言う古いはせいぜい30年前なのですが、スポーツ自転車の30年というのはとんでもない進歩の歴史で、もはや乗り物として別物です。ある時、そんな30年前の自転車をデイリー・コミューターとして使う人にオレゴン州ポートランドで会いました。2016年のことです。

今はポートランドを離れてニューポートに引っ越しをしましたが、ジョセフ・エイハーンのガレージの横を間借りしていたアーティストです。彼は動物の骨など使った作品をここで制作していたのですが、界隈では有名なサイクリストです。

それがこちらです。見た瞬間痺れました。僕の自転車観を変える1台になりました。フレームはおそらく90年代中盤ごろのSalsaですが、ロス・シェーファーがQBPにブランドを売る前のハンドメイドの時代のものです。いいのが、フォークです。ジョセフと一緒にショップをシェアしていたアイグルハート製です。いわゆるFat Chanceに当時使われていたものと同じです。これをアイグルハートにオーダーして作ってもらったのです。90年代当時にFat Chanceでフレームビルダーをしていたアイグルハートに、当時と同じ時代のSalsaのフレームに合わせて作ってもらうというのはお洒落すぎます。まさにWest Meets Eastです。

ちなみにこの人がアイグルハートさんで、少し前に引退してフランスへ移住しました。
パーツチョイスも適当に見えて相当なこだわりが伺えるのですが、シマノのRDはわざわざがロゴが消されています。そしておそらく最近のSalsaブランドのシートピラー、シートクランプ、ステムなどを使って統一感を出しながらも、ダイアコンペのブレーキレバー、ロールスのシート、ハイトライト、カンチブレーキ、リアラックなど当時物のヴィンテージパーツも使われています。フルフェンダーにフレームポンプも渋いし、極めつけはMADDENのパニアバッグです。このまったく同じパニアを探しましたし、今でもたまにebayをチェックしますが全然みつかりません。

このバッグのこともChatGPTに聞いたのですがよくわかりません。Acorn Bagsが似ていますが違うと思います。パッチがハイセンスでこれまた良いです。

ここから2年を要したのですが、実家に放置されていたクワハラに手をかけて乗れるようにしてバイクパッキングをしたのです。こちらは1991年に購入したと思うのですが、さきほどのSalsaと同じフルリジッドのバイクです。こういうベース車両を探すと分かると思いますが、良い感じになりそうなバイクを探すのはなかなか難しいです。適したバイクの条件をざっくりと書き出してみます。
- クロモリ製
- ダイアモンド型
- フォークがユニクラウン
- ブルムース以降のいわゆるTボーンタイプのステム
- フルリジッド
- サイズが大きい
もちろん素材は鉄でしょう。そして、当時物のフレームならエレベイテッドもありましたが、問答無用でダイアモンド型を。フォークに肩があると古すぎるので、ユニクラウンです。同じ理由でブルムース型のハンドル/ステムも除外。サスペンションがあるとメンテナンスが面倒だし、重くなるので当然フルリジッド。そして最後が難しいのですが、サイズ問題です。当時のMTBブームはサイズを下げてステムを伸ばすのがトレンドで、スローピングTTが神、ホリゾンタルTTはロードバイクみたいでダサいと考えられていました。なので、国内でバイクパッキングに使えそうな古いMTBフレームを探しても小さいのばかり=前三角が小さいのでバイクパッキングには不利なのです。
そして、あまりにも時代のウインドウが狭いです。1980年代後半からフォークがユニクラウンのフォークが普及し、さらに1990年代前半にはサスペンションフォークにVブレーキ、アルミフレームが普及してくるので、バイクパッキングに適した良い感じのオールドMTBというのは10年間も存在しなかったということになります。
僕の場合はたまたまその条件にジャストに当てはまるバイクが実家に長年放置されていたので軽いレストアで1泊の旅に出たのですが、走り出した直後に後悔しました。1991年の当時は何も思わなかったのですが、フレームの剛性が異常に低いのです。荷物を積んだ状態で強めにペダルを踏んでハンドルを引き付けると、あからさまにフレームがヨレるのが分かりました。フレームだけの問題ではなく、今見ると異常に細いMATRIXのリムにも問題がありそうでした。絶対にオフロードは走りたくないです。
面白いことに、なんせ自分がポジションを決めたバイクなので、ポジションだけはバッチリなのですが、問題はギア比です。前が3枚とは言え、それでも現代の基準ではハイギアードなので、激坂の上りでは瀕死になりました。そして本当に死ぬと思ったのは翌朝、山頂のキャンプ場からの下りでした。夜間に雨が降ったせいでウェットで、ブレーキレバーを握ると盛大にフォークにジャダーが発生してまとも走れないのです。
そんな訳で、せっかくレストアしたこのクワハラは再びモスボール状態に戻さました。もう乗ることはないと思います。ここから得た教訓は、30年間で機材は凄まじく進化しているし、死ぬ可能性のある自転車に於いてヴィンテージを美化するのはよくないということでした。ヴィンテージのリーバイスを穿いて死ぬことはありませんが、ヴィンテージのMTBで死ぬことはあると思ったのです。
なので、こういう90年代ヴァイブスをDNAに持つブランドが多数存在する理由が分かりました。例えばCRUST、ALL CITY、BLACK MOUNTAIN CYCLESなどは分かりやすいです。BLACK MOUNTAIN CYCLESは今でもロゴを見るとMOUNTAIN GOATに見えて仕方ないのですが、おそらくそこにはオマージュがあるのでしょう。ちなみにMOUNTAIN GOATは今でも新車が国内で買えるみたいです。
ただ、これらのブランドも昨今の物価高で一昔前のハンドメイドフレームの価格に迫っています。そういう理由でヴィンテージMTBを探す人が増えて、結果的に高騰に繋がっているのが昨今の中古事情のように見えます。
90年代初頭のアラヤ、ダイアモンドバック、GT、マングースあたりの名車が高評価を得ているのは分かるのですが、最近ではマウンテンキャット、三連勝、ブラックイーグルみたいな、当時はあまりMTBオタクが進んで買わなかったような国産ブランドのフレームまで高騰しているのを見ると、一言申したくなるのですが、「リーバイスの赤耳が2万円で買えた」という若者に対して「当時は数千円で無限に買えた」と言うオジサンはかなりウザイと思うので、そこはグッと我慢しようと思います。